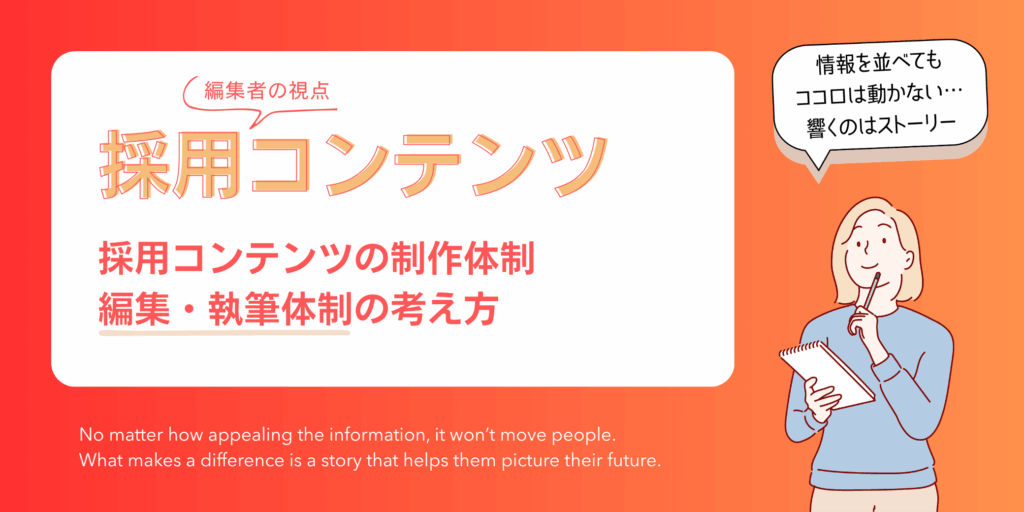
採用コンテンツで成果を出すために。編集・執筆体制を考える
採用コンテンツは、将来の組織をつくる人材との出会いをつくる重要な接点です。
本記事では、その成果を左右する「編集・執筆体制」に焦点を当て、体制の選び方や外注時の判断軸について解説します。表現の質は、体制の設計から始まります。
目次
なぜ今、採用コンテンツの解像度を上げるのか?
採用コンテンツの重要性は年々高まっています。応募のきっかけや意思決定を後押しするだけでなく、企業の魅力やカルチャーを伝えることで、採用の質を高める役割も果たします。とくに社員の声や現場のストーリーを伝えるコンテンツは、候補者の共感を呼び起こす力を持っています。
その一方で、「ライターに依頼したが、思ったような内容にならなかった」「インタビューの現場ではよかったが、記事にすると温度感が伝わらない」といった声も少なくありません。
こうした課題の背景には、制作体制の選定や発注基準があいまいなまま、制作に入ってしまっているケースが多くあります。本記事では、採用コンテンツの成果を左右する「編集・執筆体制」について、どのように検討・発注すべきかを整理していきます。
解像度を高める編集・執筆の視点とは
採用コンテンツの編集・執筆には、単に「読みやすい文章を書く」こと以上の役割が求められます。読者は応募を検討している候補者であり、目的は企業の魅力を伝えるだけでなく、働く姿を思い描き、未来の自分を重ねてもらうことにあります。
その精度を高めるには、以下のような視点が欠かせません。
- 企業理解と価値訴求の視点
経営理念や事業戦略、チーム文化など、社内の“当たり前”を言葉にして翻訳する力。とくに業界特有の用語や商習慣、ビジネスの背景まで踏まえて表現できるかどうかが、候補者の理解度や共感に大きく影響します。 - 候補者の視点に立った構成設計
働くメリットや社風、キャリアパスなど、候補者が気にする情報を過不足なく届ける構成が求められます。ただし、情報を詰め込みすぎず、地の文や発言内容で自然に補完するバランスも重要です。 - 目的と媒体に応じた文章表現
採用サイトのインタビュー、noteでのブランディング記事、SNS用短文など、媒体ごとに文体調整やトーン設計が必要です。一貫性を保ちつつ、媒体ごとに“伝わる表現”に変換できるかどうかが、発信の質を左右します。
こうした要素を丁寧に盛り込むには、編集視点に立った設計力と、企業と候補者双方にとって“納得感”のある言語化スキルが不可欠です。
編集・執筆体制のパターンと特徴
採用コンテンツの制作体制は、社内のリソース状況や発信目的によってさまざまな形が考えられます。どの体制にもメリット・デメリットがあるため、自社の状況と照らし合わせて検討することが大切です。
以下に、代表的な3つのパターンを紹介します。
| 体制 | 主な対応者 | 特徴 | 向いているケース | 留意点 |
| 社内完結型 | 採用担当者 広報など 社内メンバー | コストを抑えてスピーディに対応可能。自社理解が深く、柔軟な調整も可能。 | 記事点数が少ない、または一時的に対応したい場合/小規模組織での対応 | 構成力・表現力に課題が出やすい。継続性・客観性に不安が残ることも。 |
| ライター単発型 ※外注 | 外部ライター | 1本単位での発注が可能。執筆スピードが早く、コストも比較的安価。 | 単発記事やスピード重視の場合/トライアル的に依頼したいとき | 企画や構成の設計は自社で行う必要あり。成果物の質にばらつきが出やすい。 |
| 編集会社一括型 ※外注 | 編集者+ライター | 編集者が全体設計を担い、記事の質・トーンを安定して管理。構成・取材・原稿整理までワンストップで依頼可能。 | 複数職種・複数記事の制作/企業文化や事業内容の深い理解が必要な場合/採用広報を中長期で強化したい場合 | 初期のすり合わせや設計が成果を左右。品質相応のコストがかかる。 |
体制の特徴が見えてきたところで、実際にどう選べばよいのか。
次に、自社の状況に応じた体制の検討ポイントを整理していきます。
判断軸:どんなときに、どの体制を選ぶべきか
発注体制を検討する際には、「どの体制が一番よいか」ではなく、「自社の目的や状況に合った体制はどれか」という視点が重要です。以下のような観点で整理すると、判断しやすくなります。
▼ コンテンツの量と頻度
- 定期的に記事を更新する場合や、複数ポジションを継続募集している場合は、編集視点を持つ外部パートナーの存在が重要です。
- 1記事のみのスポット対応であれば、単発ライター発注でも対応可能です。
▼ コンテンツの目的と役割
- 「採用ブランディングを強化したい」「カルチャーを言語化したい」といった目的がある場合、構成・設計レベルから伴走できる編集チームとの連携が効果的です。
- 「募集要項をわかりやすく伝えたい」といった情報整理系のコンテンツであれば、より簡易な体制でも対応可能です。
▼ 社内の人的リソース
- 採用チームや広報担当者が多忙な場合は、進行管理や記事チェックまで任せられる編集・執筆体制が適しています。取材や撮影の場でも、社内側は内容確認に専念できるため、負担が抑えられます。
- 一方で、広報や採用担当者が記事制作に深く関与できる場合は、社内主導+外注執筆のハイブリッド体制も可能です。ただし、社内調整や撮影対応なども含めると稼働が重くなるため、工数を見積もった上での判断が必要です。
▼ パートナーとの関係性
- 採用コンテンツは、代理店やWeb制作会社に一括発注されることがほとんどです。ただし、その多くは編集部門を持たず、記事制作を都度外部に委託しているため、トーンや品質が安定しにくいという課題が生じることもあります。
- 採用に関する発信では、企業文化や事業理解をどう表現するかが成果を左右します。ナレッジを蓄積し、表現の質を安定させられるコンテンツの発注先を確保することが重要です。
こうした判断軸を事前に整理しておくことで、発注後の「なんか違った」「直しが多い」といったズレを防ぐことができます。
外注時に見ておきたい編集・執筆スキル
外注パートナーを選定する際には、見積や実績だけでなく、「どんな編集・執筆スキルを持っているか」にも目を向けるべきです。とくに採用コンテンツにおいて重要なポイントは以下の通りです。
■ 構成力とインタビュー力
現場での空気感や話のニュアンスをくみ取り、読者に届く形で再構成できるかどうか。「話は聞けているのに記事にすると浅い」場合、多くは構成力に課題があります。
■ 組織理解と翻訳力
企業の価値観や制度を、候補者が理解できる言葉に“翻訳”するスキル。たとえば 「フラットな組織」などの抽象表現を、具体的なエピソードや言葉で噛み砕く力。
■ 読者視点での表現設計
応募を検討している候補者の心理に寄り添い、「読み進めたくなる流れ」を作れているか。たとえば冒頭で何を伝えるか、どこで感情を引き出すか、といった流れの設計力が問われます。
これらは実績だけでは見えにくいため、初回の打ち合わせやトライアル記事での確認をおすすめします。オリエンの際に、ベンチマークとなる記事を用意するとお互いの目線を合わせられます。
よりよい発注のために、社内で整理すべきこと
編集・執筆を外部に依頼する際には、社内でも以下のような準備をしておくことで、やりとりがスムーズになり、成果物の精度も高まります。
● 企画・目的・ターゲットの明確化
「誰に向けて」「何を伝えたいのか」が曖昧なままだと、制作側も判断に困ります。
募集職種の背景や、読後にどう動いてほしいかなども、できるだけ共有しましょう。
● スケジュールと体制の確保
制作の進行には、社内確認・素材提供・修正確認などの対応も必要です。
関係者のスケジュールや確認体制を先に整理しておくとスムーズに進行します。
● 運用・更新を見据えた設計
単発で終わらず、将来的にシリーズ化や再発注を見据えておくと、トンマナや構成の共通化・テンプレート化が可能になります。
採用コンテンツは「制作体制」で成果が変わる
採用コンテンツには、社内の魅力を言葉に変える「翻訳力」と働く人の体験をストーリーとして紡ぐ「クリエイティブ」の両面が求められます。抽象的な企業文化や価値観を言語化し、候補者に伝わる形で表現する——その“解像度”こそが、読み手の共感や行動を左右します。
採用コンテンツは一過性の記事制作ではなく、未来の組織をつくる人材との接点を生み出す、戦略的なコミュニケーションのひとつです。だからこそ、自社が「何を」「なぜ」「どのように」伝えるのかを明確にしたうえで、ふさわしい体制を選ぶことが欠かせません。
想いや魅力をきちんと届けるために、その土台となる体制づくりから取り組んでいきましょう。
文:エクスライト編集部
