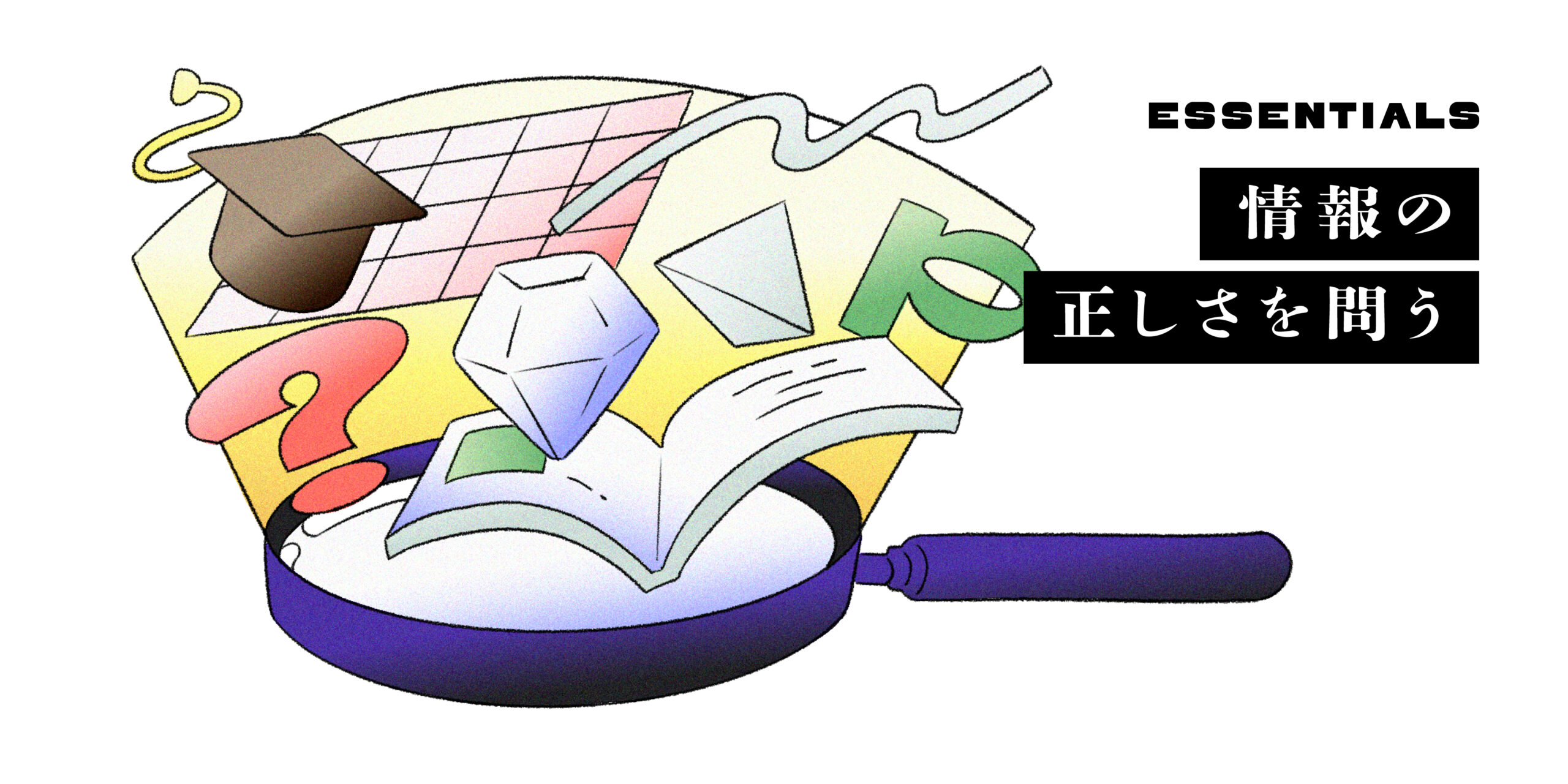
“正しい情報”はどこにある? 編集者目線のチェックポイント
SNSの普及によって、誰もが発信者になれる時代。私たちは日々さまざまな情報に触れています。中には「これって本当なの?」と不安になることや、フェイクニュース、デマなどに惑わされることも。
発信者の姿勢や責任が問われるのは、報道機関やニュースメディアに限られません。企業・団体にとっても“いかに正しい情報を発信するか”は欠かせない要素です。しかし、広大な情報の海の中で、信頼できる情報を見つけ出し、それが正しいかどうかを判断するのは容易ではありません。
この記事では、記事制作の現場において正しい情報を発信するために考えるべきポイントや、私たちが編集者として実践しているアプローチをご紹介します。
“何が正しいか?”判断するのは難しい
誰かに情報を伝えるとき、それが間違っていないかどうか、スマホやPCで調べることがありますよね。でも検索をかけてもサイトによって書かれていることが違ったり、昔聞いたはずの情報がアップデートされていたり……何が本当なのか判断するのは難しいと思います。
そもそも、絶対的に「正しい」と言える情報はあるのでしょうか? たとえば、言葉の意味や使い方は時代とともに変わります。言葉に迷う時に辞書を引くことがあると思いますが、辞書も数年おきに改訂されるので、数年前は「誤用」だった使い方が、許容されることもあります。
歴史的事実や科学的な見解も、研究が進むたびにどんどんアップデートされていきます。法律や条例などに書かれていることは「正しい」と思われがちですが、法律も改正されますし、国や地域によっても内容はかなり異なります。あるいは、特定の企業や団体、チームの中だけで適用されるルールもあるでしょう。
いま自分が所属している場所では「正解」とされていることが、一歩外に出れば「間違い」になる。だからこそ、何が正しいかを判断するのは難しいのです。
誰がどのくらい困るか?が判断の目安になる
“絶対的な正しさ”を提示するのは難しいとしても、少しでも真実に近づこうとすることは大切です。なぜなら、誤った情報を発信すると、「誰かが困るから」です。
情報は、伝わった瞬間から、読み手の行動や選択に何かしらの影響を与える可能性があります。特に、企業・団体として広く発信する情報は、影響力が大きいものです。個人間のおしゃべりの中であれば、すぐに「ごめん、間違ってた!」と言えばすむかもしれませんが、ビジネスではそうはいきません。
そう考えると、「どのくらいの人を困らせるか」という視点は、情報の正しさをチェックする上で、一つの指針になるかもしれません。全ての情報を完璧に正しく伝える、ということは難しくても、困らせる人が多いであろう情報、重大な影響を与えそうな情報については、より綿密なリサーチ、厳格な判断を行うこと。
誰かが“困るレベル”が高い情報としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
| 命に関わる情報 | 医療や健康に関する情報など |
| お金に関わる情報 | 商品やサービスの金額、経営や財務に関連したデータなど |
| 法律や条例 | 景品表示法、薬機法 そのほか国や地域ごとのガイドライン |
| 信頼に関わる情報 | 発信者のイメージや信頼を損なうような表現、ミス |
まず、どんな媒体であっても、人の命や健康に関わる情報は、慎重な取り扱いが求められます。お金に関する情報も、ちょっとした数字の間違いが大きな損失につながりかねません。
さらに、法律や条例に則っているかどうかも気をつけたいところ。広告コンテンツなどを制作する場合は、景品表示法などのガイドラインがあります。景品表示法(※1)では、消費者が安心して商品やサービスを選べるように、嘘や大げさな表現などを禁止しています。
化粧品や健康食品などを紹介するなら、薬機法(※2)も。たとえば、健康食品に「必ず痩せます」「ガンに効きます」など、効果効能を保証するような表現や、医薬品と誤解されるような表示をすることは薬機法違反にあたります(※3)。
信頼(ブランド)に関わる情報も重要です。まず、企業の名称や個人名などの固有名詞を間違えることは、その企業(人)の看板を傷つけることになり、大きく信頼を損ねるでしょう。また、どんな言葉で伝えるか、どんな表現をするかは企業のイメージを左右します。そのため、自社のブランドを大事にしている企業は、独自のポリシーに基づいて、細かな表現のルールを定めることも少なくありません。
たとえばある企業では、ジェンダー平等に配慮して、「夫婦」という表現を避け、「パートナー」「ふたり」といった表現を使うことが規定されています。細かな誤字脱字や文法的な誤りなどは、重大な情報でなければ、すぐに誰かを困らせることにはならないかもしれませんが、ミスが続くと「この企業(人)は、大丈夫だろうか?」「この商品・サービスは安心して使えるだろうか?」といった不信感につながるので、結果的にブランドを傷つけるおそれがあると言えます。
一方で、正しくても誰かが困る、人を傷つけるような情報発信もあることも心に留めておくべきです。例えば、不用意に個人情報を晒すような行為は避けるべきですし、事実であっても誰かの名誉を傷つける情報などもあります。「これを発信したら誰にどう影響するか?」という視点で考え、時には詳細な情報を伏せるというのも、重要な判断です。
正しい情報の探し方例
なるべく誰かを困らせないような発信をするために、私たちが実践している方法をいくつかご紹介します。
1. 信頼性の高いソースで確認する
「いつ」「誰」によって発信された情報なのかを必ず確認しましょう。一般的に、個人のブログやSNS投稿などよりは、公的な機関や、専門的な知見を持つ人・企業が発信する情報の方が、信頼性は高いと考えられます。
また、出版物やネット記事などを参照する場合は、できるだけ「一次資料」にあたること。例えば、実験データやアンケート結果など、調査・研究した本人によって作成された資料は「一次資料」ですが、それを引用して書かれた記事などは「二次資料」になります。「二次資料」も考え方の参考にしたり、理解を深めたりするのには役立つと思いますが、データとして掲載する場合は、一次資料まで遡って確認することで、より正確な情報を得られます。また、情報は更新されていくものなので、公開されたタイミングも必ず確認を。
2. 複数の情報を参照する
世の中には、人によって見解が分かれる情報や、正解や定義が定まっていない情報もあります。そういう時は、何か一つの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の情報源を見た上で、「どこまでのことが言えるのか」を俯瞰的に判断するようにします。
3. 監修者を立てる
専門的な知見を持つ人(機関)に見解を伺うことや、情報の誤りがないかチェックいただくことは、記事の信頼性を担保できるだけではなく、権威づけにもつながります。私たちも、特に医療や法律、金融、技術的なことなど専門性の高い話題を扱う際は、制作プロセスの中に取材や監修を組み込むようにしています。
4. 校閲を受ける
情報の正誤や誤字脱字、文法の誤りなどをチェックする、専門の校閲会社・校閲者に依頼するのも有効です。執筆者本人が見落としてしまうようなミスも、プロの客観的な目が入ることで、気がつくことができます。専門機関への依頼が難しい場合、社内で複数の人に目を通してもらうことなどでも、精度を高めることができます。
5. 実際にやってみる
レシピなどを紹介する場合は、手順や分量などが正しいかどうか、無理がないかどうか、実際に作ってみて検証してみることをおすすめします。手間を惜しまず、読者の立場に立って情報を精査することは、発信者の信頼にも繋がります。
以上のようなポイントを実践すれば、「正しい」情報にかなり近づけると思います。とはいえ、こうしたチェックは時間もコストもかかることなので、実際には毎回全てを実行するのは難しいかもしれません。掲載する媒体や発信の目的によって、どこまでのレベルを求めるべきか検討することになります。
また、情報は公開したら終わりではありません。公開後に読み手から問い合わせや指摘を受けたり、時間の経過や社会状況などを踏まえて情報を更新したりするケースもあります。なので、引用した資料の名称などをはじめ、「どこでどうやって確認した情報なのか」をしっかりと記録し、関係者の間で共有しておくことも大切です。
最近は、安全意識の高まりから食品などさまざまな製品において「トレーサビリティ」が求められていますが、それは情報においても大切な視点です。何かあった時にすぐに情報源をたどり、確認できる状態をつくっておくことが、読み手や関係者の安心につながるはずです。
大切なのは、常に自分を疑い続けること
ここまでお伝えしてきたように、「正しさ」は時代や場所、状況によって動いていくものです。間違いのない情報を求めようとしても際限がなく、どこまで・どのように伝えるのか、判断するのは難しいことです。
私たちにできるのは、その難しさを理解した上で、一つひとつの情報に対して、「本当にこれは正しいのか?」と常に疑い続けること。その姿勢を基本として、正しい情報に近づくために、さまざまなアプローチを試みることで、記事の品質が高まっていくはずです。
<参考サイト>
※1 消費者庁「事例でわかる景品表示法」パンフレットhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms201_250410_01.pdf
※2 厚生労働省ホームページ/医薬品等の広告規制についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
※3 東京都保健医療局ホームページ/医薬品的な効果効能について
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou
文:エクスライト編集部
イラスト:中尾悠(yu nakao)
