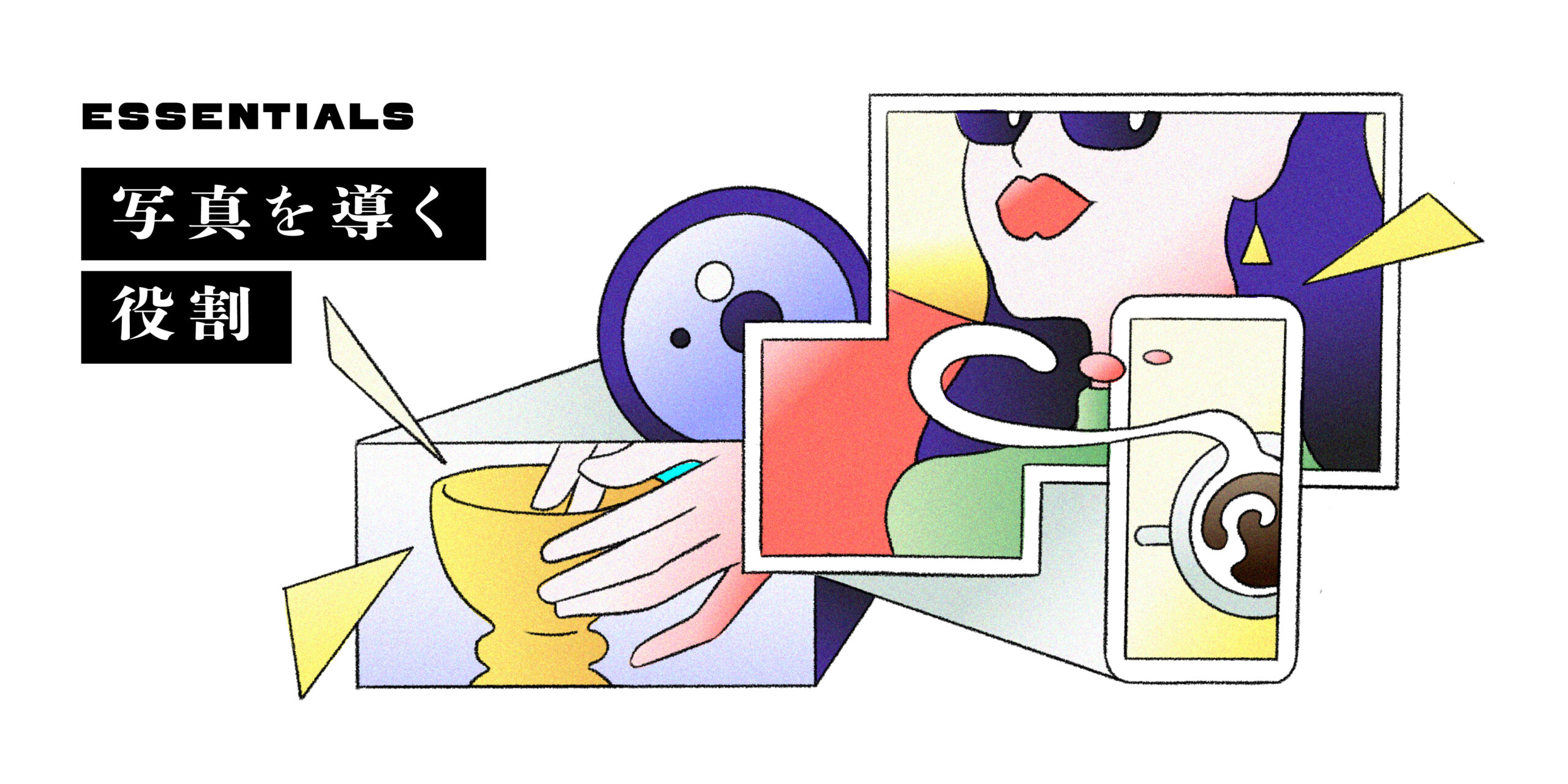
編集者が考える「ビジュアルディレクション」の作法
編集者は言葉を扱うプロフェッショナルですが、コンテンツにおいて「写真」は、ときに文章以上に力強い伝達手段となります。読者の目に最初に飛び込んでくるのは、タイトル、そしてビジュアルです。その印象は、記事の読了に大きく影響を与えます。にもかかわらず、「写真はカメラマンに任せるもの」と思ってしまってはいないでしょうか。
本記事では、編集者が担うべきフォトディレクション(あるいはビジュアルディレクション)の役割を整理し、読者やクライアントの想像を超えるビジュアルをつくるための視点をご紹介します。
目次
フォトディレクションとは何か
フォトディレクションとは、「写真の内容や印象を、編集者の視点でコントロールすること」を指します。
主な役割には、以下のようなものがあります。
- コンテンツの意図に沿った写真の方向性を考える
- 被写体・構図・シチュエーションを検討する
- カメラマンに具体的なイメージを伝える
- 撮影現場での構図やトーンの調整
- 仕上がった写真から最適なカットを選ぶ
写真を実際に撮影するのはカメラマンですが、そのビジュアルを編集的に判断し、伝えたい世界観に仕上げるのは編集者の大切な仕事です。
編集者が写真をディレクションする必要性とは
1. 文章と写真の「温度感」を合わせるため
どれほど文章が的確であっても、写真のトーンや雰囲気が異なっていれば、読者には違和感が残ってしまいます。企画の方向性や伝えたいメッセージに合った写真を選ぶことが大切です。
2. 写真は読者との“最初の接点”であるため
読者の多くは、文字よりも先に写真を見て印象を受け取ります。その一枚が、「読んでみよう」と思わせるかどうかを決定することもあります。写真は装飾ではなく、コンテンツの入り口なのです。
3. 撮影現場と記事の文脈をつなぐ存在として
カメラマンは撮影のプロですが、記事の構成や文脈まですべてを把握しているわけではありません。だからこそ、編集者が現場で意図を伝え、調整することで、写真の完成度が大きく変わります。
編集者が行うべきフォトディレクションの流れ
ここからは、編集者がフォトディレクションを行う際の流れを見ていきます。
| フェーズ | 編集者が行うこと |
|---|---|
| 撮影前 |
・撮影の目的や読者ターゲットを整理する ・イメージラフや参考写真を準備する ・必要なカットリストを作成する |
| 撮影中 |
・現場に立ち会い、構図や空気感を確認・調整する ・偶発的な「良い瞬間」を見逃さず拾い上げる |
| 撮影後 |
・使用する写真を選定する ・不要なカットを排除する ・必要に応じてトリミングやレタッチを依頼する |
この中でも特に重要なのが、撮影中の立ち回りです。
現場に行って初めて気づくことも多く、光の入り方、被写体の雰囲気、スペースの広さなどを踏まえて、その場で判断する柔軟性が求められます。撮影中の機転やひと工夫によって、写真の印象は大きく変わるのです。
フォトディレクションが不足するとどうなるか
フォトディレクションが十分でないと、以下のようなことが起こります。
- 記事の世界観と写真の印象が噛み合わなくなる
- 想定していたカットが撮れず、やや曖昧なビジュアルになる
- 写真で読者の心を動かせず、記事を読まずに離脱されてしまう
- サイト全体のビジュアルクオリティにムラが出てしまう
編集者がビジュアルを任せきりにすることで、こうした“ズレ”が生まれることがあります。これは記事全体の信頼感にも関わる要素です。
想像を超えるビジュアルをつくるための5つの問い
「いい写真」を撮ることはゴールではありません。
読者の感情に届く写真、記憶に残る写真をつくるためには、以下のような問いを常に自分自身に投げかけることが大切です。
1. この写真を見て、読者は「当たり前」と思ってしまわないか?
伝えたいことが写真の中に表現されていても、「よくある構図」「予想通りの画」であれば、読者の目には印象に残りません。当たり前すぎる写真は、記憶にも感情にも届かないのです。ほんの少しの違和感や独自性が、読者の心を留めるきっかけになります。
2. 言葉よりも先に、“感情”が動くビジュアルになっているか?
写真は視覚的な「感情のトリガー」です。論理的な理解より先に、写真を見て「楽しそう」「美しい」「切ない」など、何かしらの感情が動くことが理想です。記事に込めた思いがビジュアルにも乗っているか。直感的な反応を想像しながら選定・調整することも必要です。
3. この写真は、見る人の“解釈の余地”を残しているか?
すべてを説明し尽くすような写真は、ときに「ただの記録」になってしまいます。少しだけ情報を曖昧にする、あえて背景を写さない、視線の先を写さないなどの“余白”があることで、見る人が想像し、感情移入できるようになります。解釈の余地がある写真は、読者との「対話」を生み出してくれます。
4. どこかに「意味の違和感」や「小さなひっかかり」があるか?
目に止まる写真には、多くの場合、ちょっとした“違和感”があります。たとえば「笑顔なのに手元だけ緊張している」「料理写真に写り込んだ生活感」「真面目な記事に差し込まれたユーモラスな構図」など。意図的にずらすことで、見過ごされない写真になります。これは「編集的な遊び心」や「狙いの仕込み」とも言えます。
5. 一枚(あるいはレイアウト全体)で、世界観を表現できているか?
その一枚で、記事全体のトーンやメッセージが伝わるかどうか。あるいは複数のカットやレイアウトで、世界観に一貫性があるかどうか。色味、質感、構図、余白の使い方など、ビジュアル要素を意識的に統一することで、読者は「その世界」にスムーズに入り込むことができます。写真もまた、物語の一部なのです。
これらの問いは、読者の想像を超えるビジュアルを生み出すための道しるべになります。
おわりに:「写真も編集する」意識を持つこと
文章と同じように、写真にも「構成」や「意図」、「文脈」が存在します。編集者がフォトディレクションの意識をしっかりと持つことで、コンテンツ全体の完成度は大きく向上します。
「写真はカメラマンに任せるもの」と割り切るのではなく、「写真も編集者が最後まで責任を持つもの」として取り組むこと。それが、時代を問わず編集者に求められる姿勢であり、読者の心を動かすコンテンツづくりに必要な視点だと思います。
文:エクスライト編集部
イラスト:中尾悠(yu nakao)
